オキュラーサーフェス疾患(角膜・結膜疾患、ドライアイ)
定義
- オキュラーサーフェスとは角膜、結膜、涙液で構成される目の表面のことです。
角膜・結膜疾患
角膜、結膜、涙がお互いに影響を及ぼし合っており、どれか一つに異常が生じても他の部分の障害が生じます。
ドライアイ
涙の量が減ったり成分が変化したりして、目の表面が乾燥し、角膜や結膜に傷が生じてしまいます。
オルソケラトロジー
特徴

オルソケラトロジーは、手術をしないで近視を治す方法です。就寝中に治療用のコンタクトを装着し、角膜の中央を押さえて平らにすることで、日中の視力を回復させます。
レーシックなどの手術による治療は、いったん角膜を削ると元には戻せません。しかし、オルソケラトロジーは、レンズの装用を中断してしばらくすると、角膜が元の形に戻ります。手術による治療よりも、はるかに気軽に試していただける方法です。
日中コンタクトをしたくない方、スポーツなどをしていてコンタクトや眼鏡の装用が困難な方、レーシックなどの手術には抵抗がある方などに、おすすめです。
近視進行抑制点眼薬
特徴

昨今小児の近視が増加しており、近視が進行して強度近視と言われる状態になると、眼底の変化を生じて矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズを装用して得られる最高視力)が低下し改善できなくなったり、緑内障を発症するなど、大人の失明の大きな原因の1つとなってきています。
近視の進行を小児期から抑えることで強度近視にならないようにしていくことが大切と思われます。
近視の進行を遅らせる方法としては、低濃度アトロピン点眼薬がオルソケラトロジーと同程度に効果があることがわかりました。
”マイオピン”はシンガポールで開発された低濃度アトロピン点眼薬で、日本でも多施設研究で6歳から12歳の効果があることが報告されています。
また”リジュセアミニ点眼”が2025年4月に日本国内で発売されました。
緑内障
症状

緑内障とは、目で見た情報を脳に伝える「視神経」がダメージを受けて、視神経線維の数が減る、中高年の方によくみられる病気です。「急性緑内障」と「慢性緑内障」があります。
急性緑内障とは、角膜(黒目)と虹彩(茶目)の隙間が狭い方に、さまざまな条件が重なった場合、眼圧が急上昇して、目の痛みや頭痛、視力低下、充血などの症状が起きることです。今まで近視がなかった方は、加齢とともに発作を起こす場合もあります。急激な目の激痛とかすみ、充血が生じた場合は、なるべく早く受診しましょう。
一方、慢性緑内障は初期には自覚症状がないことが要注意点です。少しずつ視野が狭くなるため、視力低下に気付く頃には、緑内障の症状がかなり進行しています。自覚症状がないからと放置したり、治療を中断すると知らず知らずのうちに進行します。治療開始が遅いと、最悪の場合は失明する恐れもあります。
治療
緑内障の治療には、眼圧を下げる効果の高い点眼薬を使用します。点眼薬で対応できない場合は、手術で眼圧を下げます。治療を開始したら、薬の使用と定期的な受診を継続してください。緑内障は進行の度合いを自覚しにくいため、自己判断で中断すると悪化につながる恐れがあります。
緑内障は早期発見が何よりも重要です。健康診断などで緑内障の疑いを指摘されたら、必ず眼科を受診しましょう。また、他の症状で眼科を受診した場合も、緑内障がないかどうかを診てもらうことが大切です。
加齢黄斑変性
症状

加齢黄斑変性は、網膜の中心にある「黄斑」という部分が、加齢に伴ってダメージを受け、ものがゆがんで見えたり、大きさが変わって見えたり、視力低下を引き起こしたりする病気です。
網膜は、目に入る光の刺激をキャッチして、視神経に信号を伝達する働きがあります。しかし、加齢黄斑変性になると、刺激をキャッチできなくなり、その伝達に不都合が生じます。緑内障と同じく、最悪の場合は失明する恐れもある病気です。
治療
加齢黄斑変性は、左右で症状に違いが生じる方が多いですが、中には両方の目で同じように発症する方もいます。主な治療法は「抗VEGF療法」です。
当院で検査を受けた患者さまに「加齢黄斑変性の治療の必要性がある」と判断した場合は、適切な治療を受けることができる医療機関にご紹介いたします。
小児眼科

小児眼科とは、まだ目が完全に発達していないお子様が対象の眼科診療です。
視力が発達していく中で、ものをはっきりみることが出来ない状態が続くと、弱視となってしまう可能性があるので、ご不安な方などは一度受診されることをおすすめします。
眼鏡処方・コンタクト作成
コンタクトレンズ作成
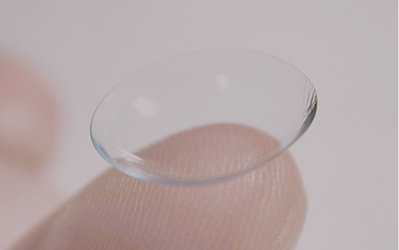
視力検査や眼の検査の後、コンタクトのトライアルレンズを装用して、レンズのフィッティングを確認、再度装用後の視力検査を行い、レンズを決定します。
当院では、お使いになっているレンズの種類や度を把握して最適な状態をお勧めするために、基本的にはコンタクト処方箋を外部にはお出ししておりません。コンタクトレンズを続けて装用される方は、レンズ装用視力、アレルギー性結膜炎がないか、角膜の状態は異常ないかなど、3ヶ月に1回の検診を継続されると安心です。コンタクトレンズによる重篤な障害も報告されていますので、定期検査で予防していくことが大切です。
眼鏡処方までの流れ

まず視力検査を行います。その後目に合った度数を検眼枠に入れて、実際に装用して見え方を確認していただきます。このとき遠くの見え方、本や新聞などの近くの見え方をご確認ください。
老眼のある場合、眼鏡のレンズの種類は用途に合わせて選ぶ必要があります。屋外でも遠くが見えるようにするには遠近両用眼鏡、屋内中心で近い距離も見やすくするには中近、デスクワーク中心でよければ近々などがあります。最適なレンズを選びましょう。
装用していただき、見やすいことを確認してから眼鏡処方いたします。
その他一般眼科
症状

- 近視
- 老眼
- 目がかゆい(花粉症)
- 目のかすみ(白内障)
- 目の充血(結膜炎・強膜炎など)
- 視力低下、視野欠損(網膜剥離)
- 髪の毛や虫のようなものが見える(飛蚊症)
治療
- 眼鏡処方・コンタクト作成
- 点眼薬
- 内服薬
- 網膜剥離治療(レーザー光凝固)
